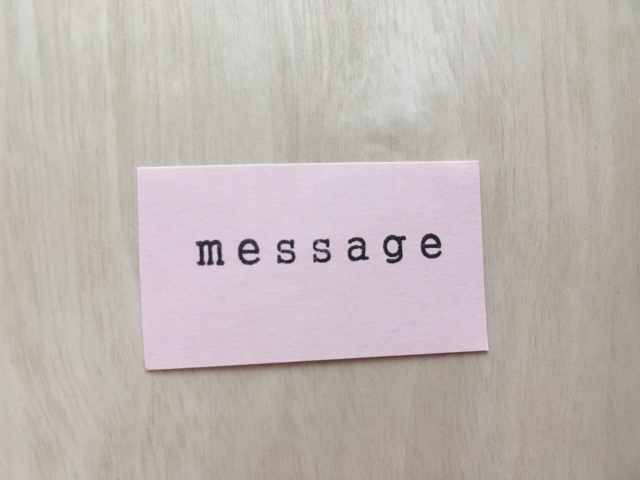電報は、ビジネスシーンや冠婚葬祭などの特別な場面で使われる伝統的なメッセージ伝達手段です。しかし、現代ではメールやSNSの普及により、電報を送る機会が減り、送り方がわからない方も多いのではないでしょうか。
このページでは、初心者でも安心して
電報を送れる方法や、便利なサービスについて詳しく解説します。
電報とは何か?
電報とは、簡潔なメッセージを遠くにいる相手に迅速に伝えるための電気通信サービスです。もともとは19世紀にモールス信号を用いた電信技術として登場し、当時は国際的な通信手段として非常に重宝されていました。
モールス信号とは、短音と長音を組み合わせた符号を使って文字を伝えるシステムで、これにより文字を打電し、遠方の受信者にメッセージを伝えることが可能でした。
時代が進むにつれて、電報は日本国内でも広く利用されるようになりました。特に戦前・戦中は、緊急の連絡や公式な通知手段として多用されており、戦地からの連絡や政府からの公式発表にも使われていました。
当時は、郵便局などの窓口に出向き、メッセージを手書きで伝えて電報として送付するのが一般的な手段でした。送られたメッセージは電信機を通じて変換され、受信側では再び文字として印字され、届けられるという流れです。
現代の電報は、インターネットや電話を使ったサービスが主流となっています。特にオンライン電報サービスでは、パソコンやスマートフォンから簡単に申し込むことができ、手軽に送れるようになっています。
オンラインでの申し込み手順は、まずサービスのウェブサイトにアクセスし、送りたいメッセージを入力、送り先の情報を登録します。その後、決済を行うことで、指定された日時に相手に届けられます。
電報はその特性上、ビジネスシーンや冠婚葬祭など、特別な場面で使われることが多いです。例えば、結婚式に出席できない場合に「心からのお祝いを申し上げます」といったメッセージを添えて祝電を送ったり、お悔やみの場面で「心よりご冥福をお祈りいたします」といった弔電を送ったりします。
また、ビジネスでは取引先の会社の創立記念日や、上司の栄転のお祝いなど、フォーマルな場面でも非常に役立ちます。
電報の形式も、紙に印刷されたメッセージカードとして届けられることが一般的です。特にお祝い用の電報では、華やかなデザインのカードや、花や小物を添えたギフト形式のものも選べます。
一方、弔電ではシンプルかつ落ち着いたデザインのカードが主流で、故人やご遺族への敬意を示すことができます。
初心者でも迷わない手順とポイント
送る手順はシンプルですが、いくつかのポイントを押さえることで、よりスムーズに送ることができます。
まず、送り先の情報を正確に準備することが重要です。具体的には、受取人の名前、住所、連絡先などを間違いなく確認しておきましょう。特に冠婚葬祭の際には、会場名や式典の開始時間も把握しておくと安心です。
次に、送るメッセージの内容を考えます。お祝いの場合はポジティブな表現や華やかな言葉を選び、お悔やみの場合は落ち着いた言葉や哀悼の意を表現するメッセージが適しています。ビジネスシーンでは、礼儀正しく、簡潔なメッセージを心がけることが大切です。
サービスを利用する際には、オンライン電報サービスが特におすすめです。スマートフォンやパソコンから簡単に申し込むことができ、メッセージの文例も豊富に揃っています。また、申し込みから配送までの流れがわかりやすく、急ぎの場合でも即日配送に対応しているサービスもあります。
最後に、支払い方法や配達日を確認します。多くのオンラインサービスでは、クレジットカードやコンビニ払い、キャリア決済など、さまざまな支払い方法に対応しているため、自分に合った方法を選べます。
送る際の注意点とマナー
送る際には、特にマナーを守ることが求められます。まず、メッセージは簡潔かつ丁寧な表現を心がけましょう。長文は避け、要点をまとめて伝えることで、より相手に伝わりやすくなります。また、メッセージに使用する言葉にも注意が必要です。
特にお悔やみの電報を送る際には、忌み言葉(いみことば)を避けることがマナーです。「死」や「苦」、「終わる」など、ネガティブな印象を与える言葉は使わないようにしましょう。また、お祝いの場面でも、「切れる」や「壊れる」といった不吉な言葉は避け、明るく前向きな表現を選びます。
電報を送るタイミングにも配慮が必要です。例えば、結婚式の場合は式が始まる前に電報が届くように手配するのが望ましいです。一方、お悔やみの場合は、訃報を聞いてすぐに送ることで、相手に対する誠意を示すことができます。
急ぎの場合には、即日配送可能なサービスを利用することで、確実にタイミングよく届けることができます。また、電報を送った後も、相手に届いたことを確認しておくと、より安心です。